『名もなき人たちのテーブル』マイケル・オンダーチェ【読書感想】
初稿:
更新:
- 13 min read -
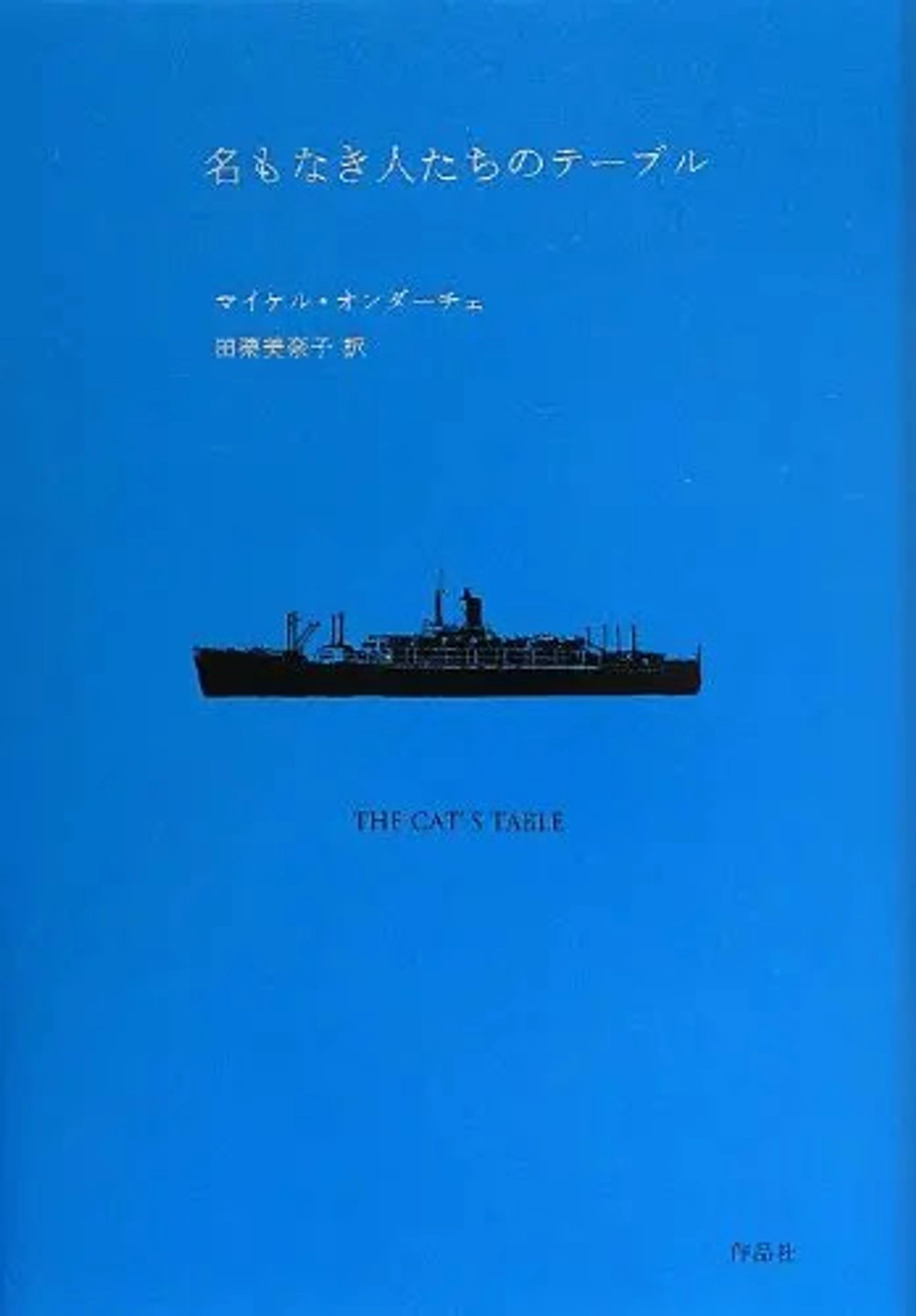
あらすじ
11歳の少年の、故国からイギリスへの3週間の船旅。それは彼らの人生を、大きく変えるものだった。仲間たちや個性豊かな同船客との交わり、従姉への淡い 恋心、そして波瀾に満ちた航海の終わりを不穏に彩る謎の事件。映画『イングリッシュ・ペイシェント』原作作家が描き出す、せつなくも美しい冒険譚。 — 本書より引用
読書感想
もし生まれ変わるならば子ども時代に大きな船で二十一日間の旅をしたい。 船は大きければ大きいほどよく、船名が「オロンセイ号」であればなお良し、そこは世界の縮図である。
そして上流に済む人々のテーブルからもっとも離れた<キャッツテーブル>に集う人々から人生を学び、旅の終わりに悲しみと共に大人になるのだ。
この物語の主人公、マイナのように。
本作は一九五〇年代、二十一日間の船旅で、当時のスリランカ(セイロン)から、離婚してイギリスで暮らす母の元へと渡った少年が語る船上体験とその後の物語である。
彼の名はマイケル、船上で出会う人々の間では「マイナ」と呼ばれており、著者と同じ名前の少年である。 著者、訳者のあとがきで触れられているが、彼がたどる人生は著者のそれと重なる部分が多い。
大型客船は階級社会の縮図だという話を聞いたことがあるが、マイナが乗船した「オロンセイ号」もまたそうであり、彼が「キャッツテーブル」と呼ぶ食堂で割り当てられたテーブルは上流階級の者たちからもっとも離れた場所にある。
面白いこと、有意義なことは、たいてい、何の権力もない場所でひっそりと起こるものだ。 — 本書より引用
そしてキャッツテーブルに集まる面々が語り、そして引き起こす物語はこれが真実であることを証明する。
マイナは船上で二人の同年代の友を得る。
カシウスは、彼のエピソードを読むとそれは小さな反逆者そのものであり、そんな彼の冒険心あふれる振る舞いはマイナに大きな影響を与える。
もう一人のラマディンは心臓に病を抱えており、それが彼の慎重さを一層濃いものとしている。活発な2人とバランスを保つ役割を果たす。
とにかく船上でのマイナとカシウスの腕白ぶりは凄まじく、しばしばラマディンもそれに引きずられることとなり、笑いをこらえる場面が何度もあった。
二十一日間のあいだ、同じ日を二度生きないことを体現し続けるこの三人組からはほんとうに目が離せない。
そんな彼らにさまざまな影響を与えるキャッツテーブルの大人たちも個性豊かな面々である。
- デッキの椅子で本を読み気に入らなければ海へと放り投げるミス・ラスケティ。
- ピアノの名手であり芸術を通じて人間の真理を愉快に語るマックス・マザッパ。
- 数々の港で船の解体工として慣らし船を知り尽くした男ネヴィル。
- 船倉に植物園を持つ植物学者でマイナの従姉に熱をあげるラリー・ダニエルズ。
そして物言わぬ仕立屋グネセケラ、彼は後半この物語にスリルを加えてくれる。
そこは大型客船、世界の縮図、爵位を持つ金持ちからイギリスへ護送中の囚人まで、キャッツテーブルのメンバー以外にも二十一日間のドラマを彩る多くの人物が登場する。
その中でフォンセカという教師になるためイギリスへ渡る人物がおり、私はとくにこの人物が好きになった。 少し長いがマイナが語る彼の人物評を引用する。
フォンセカさんは読んだ本から、安心させてくれるもの、心を静めてくれるものを引き出してくるようだった。 — 本書より引用
彼がそんなあれこれを覚えているのは、自分の考えをはっきりさせるためだったのではないかと思う。カーディガンのボタンをきちんと留めて、自力で暖まろうとする人のように。フォンセカさんが金持ちになることはないだろう。都会のどこかで教師として送る生活は、質素なものになるに違いない。だが、彼には、自分の求める生き方を選んだことによる穏やかさがあった。そして、そんな穏やかさと確信は、本という鎧で身を守る人にだけ見られるものだった。 — 本書より引用
冒頭で「オロンセイ号」の乗員になりたいと書いたが、とくにフォンセカさんに会ってみたいというのが大きな理由かもしれない。
やがて船はイギリスに到着し、物語は大人になったマイナの人生と、二十一日間の船旅で明かされなかった謎に迫っていく。
読み終えて、わずか二十一日間の旅は一人の少年が大人へと変わる人生の中でもっとも儚くそして濃密な時間であることがわかる。
本作には人生物語、旅物語、ちょっとしたミステリなど数多くの要素が含まれており、またところどころ下品で、皮肉のこもったユーモアが溢れている点が私好みであった。
(途中途中で登場する謎の試験問題集、チクリと刺さる皮肉が効いておりとても楽しめる)
船上にはマイナの従姉エミリーが乗船しており、彼女の存在はとても大切であるのだが、後に本作を再び読み返すであろう未来の自分のために多くを触れないでおく。
著者・訳者について
マイケル・オンダーチェ(Michael Ondaatje)
1943年、スリランカ(当時セイロン)のコロンボで、オランダ人、タミル人、シンハラ人の血を引く裕福な両親のもとに生まれる。54年に母親とともにイギリスに渡り、62年にはカナダに移住。トロント大学、クイーンズ大学で学んだのち、ヨーク大学などで文学を教える。詩人として出発し、71年にカナダ総督文学賞を受賞した『ビリー・ザ・キッド全仕事』ほか十数冊の詩集がある。76年に『バディ・ボールデンを覚えているか』で小説家デビュー。92年の『イギリス人の患者』は英国ブッカー賞を受賞(アカデミー賞九部門に輝いて話題を呼んだ映画『イングリッシュ・ペイシェント』の原作)。また『アニルの亡霊』はギラー賞、メディシス賞などを受賞。小説はほかに『ディビザデロ通り』、『家族を駆け抜けて』、『ライオンの皮をまとって』など。本書『名もなき人たちのテーブル』は自伝的要素が色濃く見られるフィクション作品。現在はトロント在住で、作家・編集者の妻とともに文芸誌「Brick」を刊行。カナダでもっとも重要な現代作家のひとりである。 — 本書より引用
田栗美奈子(たぐり・みなこ)
翻訳家。訳書に、ラナ・シトロン『ハニー・トラップ探偵社』、リチャード・フライシャー『マックス・フライシャー アニメーションの天才的変革者』、ジョン・バクスター『ウディ・アレン バイオグラフィー』(以上作品社)他多数。 — 本書より引用
メモ
タイトルがある章とない章がある。ナゼだろうか?
引用メモ
彼がそんなあれこれを覚えているのは、自分の考えをはっきりさせるためだったのではないかと思う。カーディガンのボタンをきちんと留めて、自力で暖まろうとする人のように。フォンセカさんが金持ちになることはないだろう。都会のどこかで教師として送る生活は、質素なものになるに違いない。だが、彼には、自分の求める生き方を選んだことによる穏やかさがあった。そして、そんな穏やかさと確信は、本という鎧で身を守る人にだけ見られるものだった。 — P66より引用
面白いこと、有意義なことは、たいてい、何の権力もない場所でひっそりと起こるものだ。陳腐なお世辞で結びついた主賓席では、永遠の価値を持つようなことはたいして起こらない。すでに力を持つ人々は、自分で作ったお決まりのわだちに沿って歩みつづけるだけなのだ。 — P84より引用
どのみち「死」はそこにある。または、「運命」というもっと厄介な観念と言い換えてもいい。 — P122より引用
それまで僕は、自分にとって欠かせない、ささやかな防御の柵を張りめぐらせて、そのなかにこもって身を守ってきた。それが僕という人間を形作っていたのだが、もはやその柵は消えていた。 — P128より引用
いきなり家に帰ったら、女房があるミュージシャンと一緒にいたんだ。そして彼はミス・ラスケティにこう打ち明けた。「もし銃を持ってたら、そいつの心臓に一発お見舞いしていたところだ。だが、部屋にあったのは、やつのウクレレだけだった」 — P188より引用