『精神の氷点』 大西巨人 【読書感想】
初稿:
更新:
- 8 min read -
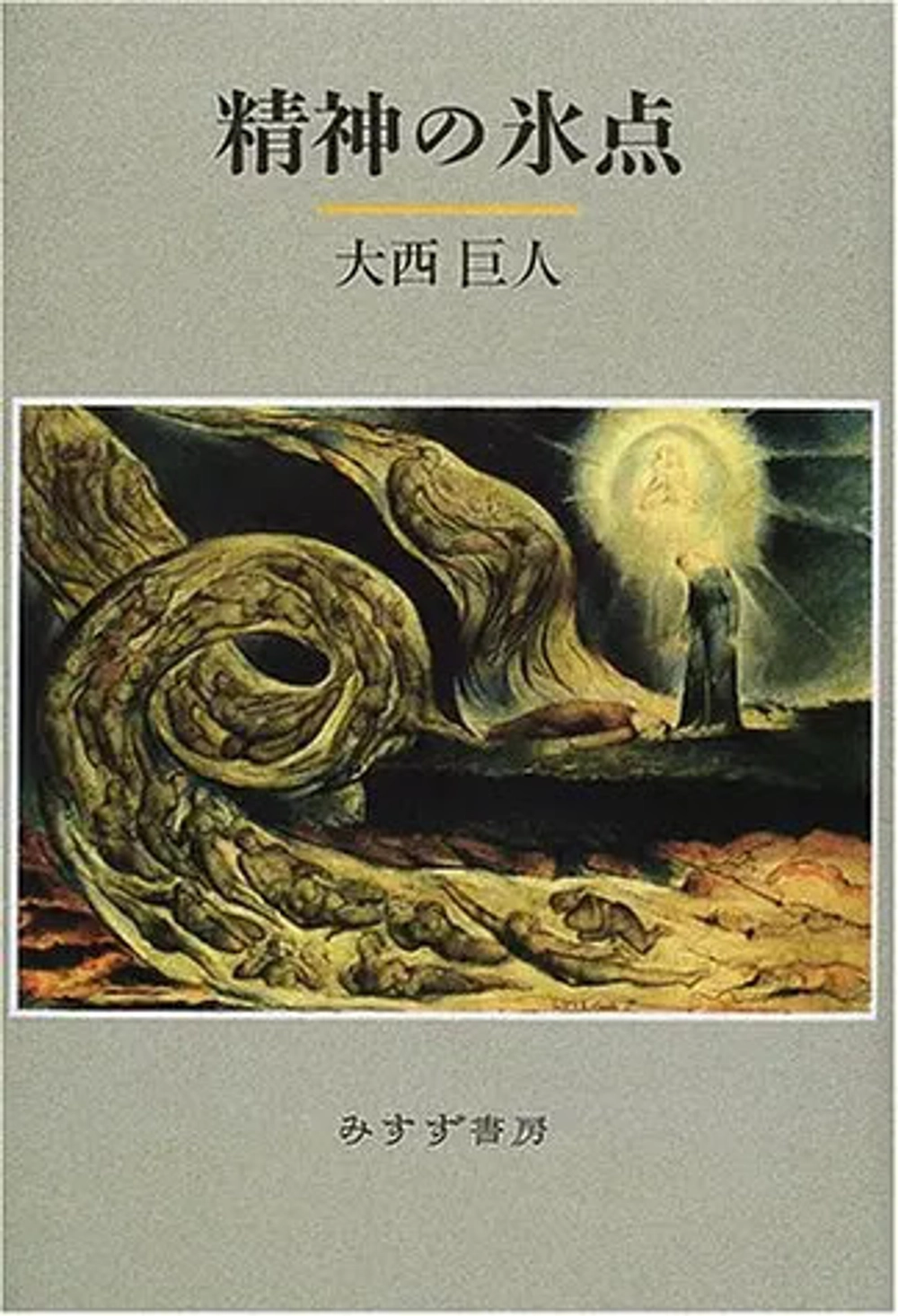
あらすじ
泥水溜りの中に歪み縮かまった投影は、復員後ふた月の水村宏紀を表象していた。そこには「地獄」を見つめてきた陰鬱な眼がある-。一人の復員兵が彷徨する「魂と虚無」の相克を描く。改造社1949年刊の長篇に字句修正加筆。 — 本書より引用
読書感想
何という小説であるか。 巻末のおくがきにて著者自身は「この未完の異様なもの」と、本作品について記すとおり、先の大戦前後を舞台に己を捉え続けるエゴと現実との狭間で凄まじい葛藤を見せつける男の物語は言いようのない異様さを呈している。
戦争から復員した青年「水村宏紀」は焼け野原となった故郷へと戻り、以前に関わりのあった女性「志保子」と遭遇し己の過去と再び向き合う。
再会した女性「志保子」はかつて彼が踏みにじった女性のひとりであり「現実」の「追求の鞭」のきびしさとも彼に思われた。 — 本書より引用
敗戦状況下でかつての知った顔を頼りに通ってくるようになった志保子に対し、水村にとって彼女は、過去や現実との対峙することを強いる存在であると同時に、己のどす黒い欲望を喚起する肉体でしかない。
著者が「魂の黒点」、「罪悪の極印」と描写する水村の過去とは何か。
時代は1930年代後半、水村の青春時代は無残なものである。
世界が蛮力を競い合う時代、当時の日本は平和を希求し思想することを反国家とする、絶対封建国家である。数少ない友人のひとりは、検挙され、「必ずあいつをやる」と言い残し自殺した。「あいつ」とは当時の国家元首であろう。
「何もかも、どうでもよい。やがて、おれも、戦争に引っ張りだされる。それも、よかろう。」 — 本書より引用
高校時代まで微かに希望を抱いていた水村であるが、それは国家の暴力により無残にも破壊されてしまった。
これが彼の心に巨大な虚無を生み出した。
水村という男は自制を持ち合わせない極端に生真面目でおよそ回転の早い思考の人間であると思われる。
しかし極端に弱く、極端に生真面目な人間は悲劇的である。
この虚無は、彼を絶望への反動として一切を否定し尽くすことに向かわせ、「精神と肉体は一致・同一化するべき」との屈折した強迫観念を植え付ける。
その結果として彼は盗みを働き、次々と周囲の女性を冷徹に籠絡する。(志保子もそのうちの一人)ついには戦争に駆り出される前、殺人を果たすに至る。
しかし、戦争は彼を殺さず、世界を滅亡させることはなかった。
消えるはずの、消滅するはずの虚無や過去や未来が残ってしまった。
欲望は「生」の証でもある。
しかし水村という男は過去に自分を縛り付け、欲望はエゴと封し、すべての意味を否定することだけを証明しなければならないとする。
そんな人間が人間らしい温度を保つことは不可能であり、彼の精神はある一点に向かいだんだんと冷えていくように感じる。
最終的に彼が下した決断は法の裁きであり、彼がたどり着くその地点、それが本書のタイトル「精神の氷点」とふと頭の中で重なる。
読後のいま、悲劇を通り越し、虚無感しかない。
あまりにも心のありようが生めかしく描写されており、実際に暗く重苦しい時代を生きた者の独白のような、もしかすれば私小説ではないかとも感じる作品であった。
著者について
大西 巨人(おおにし きょじん、1916年(大正5年)[1]8月20日 - 2014年(平成26年)3月12日)は、福岡県福岡市出身の小説家・評論家。本名は同じく「巨人」と書いて「のりと」。マルクス主義の立場を堅持し、唯物論的観点から個人の尊厳を創作で追究した。小説・批評のいずれにおいても、常に主体を明確にした、論理性を重んじる文体を用いている。 — 本書より引用
メモ
貪婪(どんらん)
飽くことを知らないこと。大変に欲深であること。また、そのさま。貪欲。たんらん。「-な金銭欲」「-な好奇心」
淪落(りんらく)
おちぶれること。身をもちくずすこと。堕落。「淫蕩の地に-する/新聞雑誌 58」
玄翁(げんのう)
玄翁とは、頭部の両端がとがっていない金槌。大工がのみを叩いたり、石工が石を割るときに用いる。
むすぼおれ
むすぼ・れる【結ぼれる】結ばれて解けにくくなる。心にわだかまる。関係をつくる。縁故 になる。
深甚(しんじん)
意味や気持ちなどが非常に深いこと。また、そのさま。甚深。「―な(の)謝意を表する」