『孤児列車』 クリスティナ・ベイカー・クライン 【読書感想】
初稿:
更新:
- 13 min read -
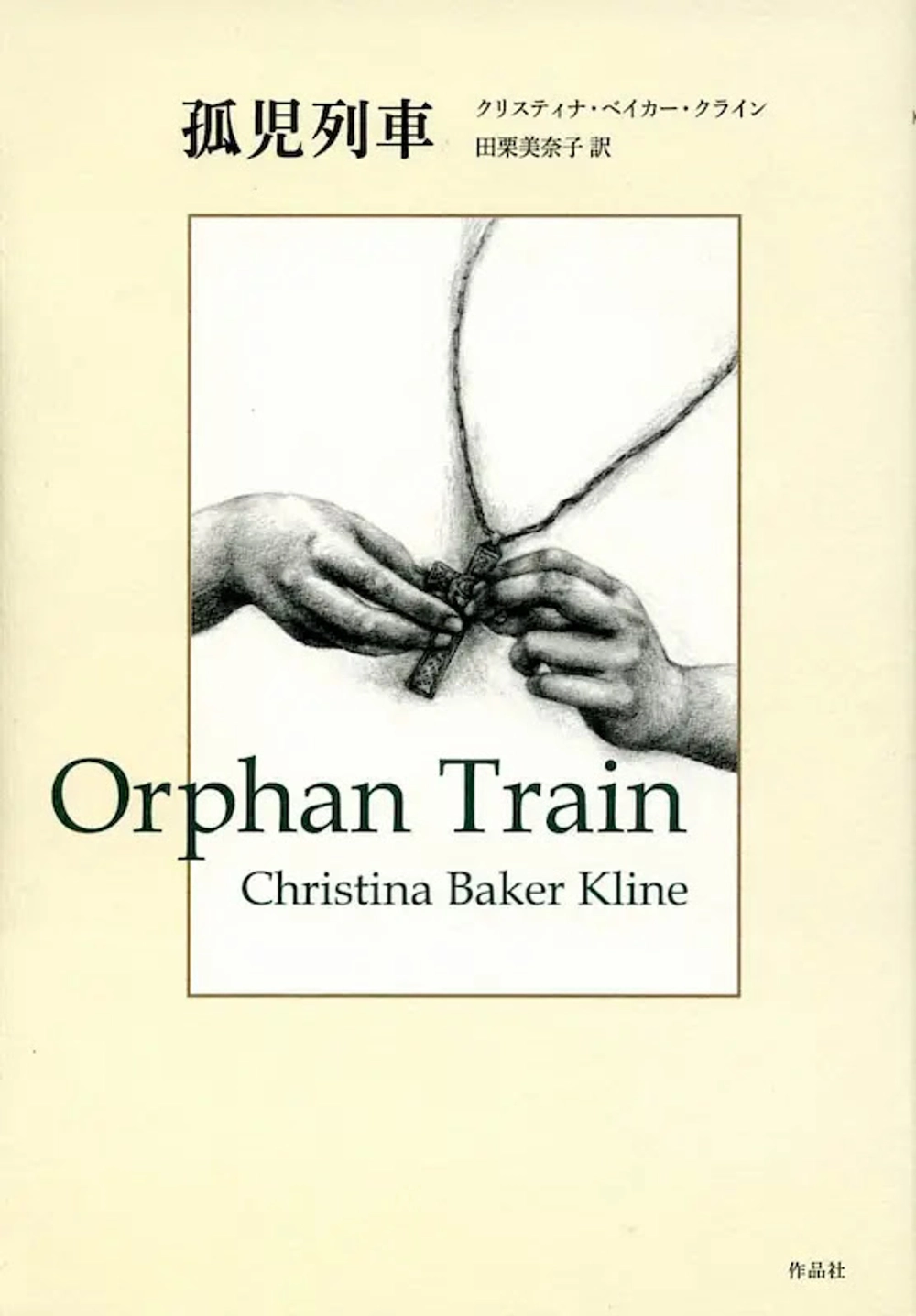
あらすじ
91歳の老婦人が、17歳の不良少女に語った、あまりにも数奇な人生の物語。
火事による一家の死、孤児としての過酷な少女時代、ようやく見つけた自分の居場所、長いあいだ想いつづけた相手との奇跡的な再会、そしてその結末……。すべてを知ったとき、少女モリーが老婦人ヴィヴィアンのために取った行動とは――。 — 本書より引用
感想
振り返ってみると、喜怒哀楽、すべての感情が限界に振れたのではないかと思う。
物語の概要
物語の主人公であるニ人の女性「モリー」と「ヴィヴィアン」。
本書はニ人が出会う二〇一一年とヴィヴィアンの少女時代の2つが織り成すように進んでいく。
二〇一一年、十七歳という年齢を生きる少女モリーは、耳や鼻にありったけのピアスを施し、髪を黒く染めて紫と白のラインでアクセントを入れ、腰にはタトゥーがある。妥協することが容易ではない人生を歩む彼女にはこのぐらいの重武装が必要なのであろう。
そんなモリーはトラブルを起こし、五十時間の奉仕活動を行うことになる。内容は大きな屋敷の荷物整理、そして屋敷の主人が九十一歳のヴィヴィアンである。二人は屋根裏部屋にある大量の荷物をひとつずつ開けていく。そこには壮絶な少女時代を過ごしてきたヴィヴィアンの人生を物語る品々が納められていた。
モリーとヴィヴィアン、二人の共通点と関係
七十以上も歳の離れたニ人であるが、共通する点がいくつもある。2人とも孤児であること、差別を受けやすいルーツ(モリーはネイティブインディアンの父を持ち、ヴィヴィアンはアイリッシュ)であること、「期待を持たなければ絶えることが楽になること」を体験的に熟知している、などなど。
あなたって、苦労せずに本音を言えるのね? — 本書より引用
取り繕うことが苦手なモリーをヴィヴィアンは初対面ですんなり受け入れる。きっと言葉にせずとも通じ合うものを感じたからであろう。
「モリーのための奉仕活動」であるが、その実はヴィヴィアンの長い人生をたどる旅であり、しだいにモリーはヴィヴィアンの人生から大きな影響を受ける。
ヴィヴィアンの壮絶な人生
最後にクライマックスがあるものの、ヴィヴィアンの人生をたどる部分だけで充分に素晴らしい文学作品である。さまざまな局面で彼女が見せる振る舞いに胸を打たれる。
ヴィヴィアンはアイルランド人で本当の名を「ニーヴ」と言う(以降、ニーヴと記載)。七歳のときに移民として一家五人でアメリカに渡ってきた。九歳のとき火事に合い、アメリカに来てから生まれた妹を含む家族全員を失い孤児となる。
タイトルの「孤児列車」は実際に存在したものだという。
一八五四年から一九二九年のあいだに、いわゆる孤児列車は、親をなくした子、捨てられた子、家のない子を、二〇万人以上も運んだ。多くの子は、本書の主人公と同じく、アイルランドからのカトリック移民の一世だった。列車はアメリカの東海岸の歳から中西部へ、”養子縁組”のために向かったが、結果としては年季奉公になることが多かった。 — 本書~巻末『附録2 孤児列車小史』より引用
里親=賃金を払わない雇用主、バーン家
ニーヴは孤児列車の乗客となり、最初の里親(賃金を払わない雇用主とも言える)、バーン夫妻の元に引き取られる。針子として働き、廊下に藁布団で眠り、少ない食事で痩せ細っていく。時代は一九二九年、世界恐慌が起き不況に見舞われたバーン夫妻は針子を次々に解雇する。
「その子は食べ過ぎなんですよ!」 — 本書より引用
痩せ衰えたニーヴにバーン婦人が最後に言い放った言葉である。
ワイルド・アメリカ、グロート家
無計画に子どもを次々と設けるが、母親は寝たきり、父親は「社会に出たら負け」と自給自足を試みる甲斐性無し。ニーヴは子守を宛てに引き取られるが、寝ている間に隙間からの雪に埋もれ、垢にまみれ、リスを煮て食べる文明から切り離された無秩序な暮らしは悲惨を極める。
結局深夜、父親に襲い掛かられ、騒ぎに気付いて起き上がった母親に「ビッチ、出て行け!」と吹雪の中、追い出される。
次の引受先で生活はようやくまともになり素晴らしい再会もあるが、やはり失い続ける彼女の人生は変わらない。幸せはやがて去っていくものであり、大切な人はその姿を消し幽霊として存在し続けるもの、そんな人生観に行き着いてしまったニーヴは、自らの手で手放す行為に及ぶ。
失うという事態は、起こりうるだけでなく、避けられないものだと、ずっと昔に学んだ。すべてを失うこと、一つの人生を手放して別の人生を見つけるとはどういうことか、わたしは知っている。そして今、奇妙な深い確信とともに思う。その教訓を何度もくり返し突きつけられることが、わたしに与えられた運命に違いない。 — 本書より引用
家族への憧憬、そしてクライマックスへ
「家族」に対する憧れは、彼女の心の奥底に強く存在する。辛い状況下において彼女は常に小さな家族を夢想する。
わたしたちは奇妙な小家族になった。
~ 孤児列車の車中、腕白なダッチー、赤ん坊カーミーと
— 本書より引用
ここでは女性たちの小さな集団が、わたしにとって家族みたいなものになっている。 ~(略)~ バーン家の針子たちと — 本書より引用
しかし、失うことに慣れてしまった彼女は憧れや想いを固い殻に閉じ込めて封印してしまったのであろう。屋根裏部屋の荷物のように。
時代背景や貧困の度合いなど深さは異なるものの、若きニーヴの振る舞いは所々でモリーと重なる。モリーは少女ニーヴの人生に大きく揺さぶられ、その揺れはこちらにも伝わてっくる。「失ったものを何とかしたい!」
モリーとニーヴ、二人の少女は時代を超えて出会った。ニーヴはモリーに影響を与え成長を促し、モリーは九十一歳になったニーヴ、つまりヴィヴィアンの背中を押す。
過去は必要なものであったと確信できたときの人間はたまらなく美しい。
二人は固く殻に閉じこめていた柔らかい魂を互いに解放し合ったようにも見える。
読中、ニーヴが首もとのケルト十字に触れる度、カバーに描かれている絵を眺めた。
読み終えた今、再びその絵を眺めながら彼女の長い人生を共にしたそのお守りが、失ったはずの大切な者たちへと導いたのだろうと思う。
小さなケルト十字に感謝を、ニーヴ、モリーに賛辞を、月並みな言葉だがほんとうに素晴らしい作品だった。
著者・訳者について
クリスティナ・ベイカー・クライン(Christina Baker Kline)
小説家・ノンフィクション作家・編集者。小説は本書のほかに、Bird in Hand 、The Way Life Should Be、Desire Lines 、Sweet Waterの四作がある。出産から子育ての期間に、Child of MineとRoom toGrowというオリジナルのエッセイ集二作を企画・編集し、いずれも高い評価を得る。また、フェミニストの母親たちと娘たちに関する本TheConversation Beginsを母親のクリスティナ・L・ベイカーと共同執筆。About Face:Women Write AboutWhat They See When They Look in theMirrorをアン・バートと共同編集。イングランド、テネシー州、メイン州で子ども時代を送り、その後はミネソタ州、夫の育ったノースダコタ州で、多くの時間をすごす。イェール大学、ケンブリッジ大学を卒業し、ヴァージニア大学では小説創作コースの特別研究員をつとめる。フォーダム大学やイェール大学などで創作や文学を教え、最近ではジェラルディン・R・ドッジ財団から奨励金を得ている。家族とともにニュージャージー州のモントクレア在住。 — 本書より引用
田栗美奈子(たぐり・みなこ)
翻訳家。訳書に、マイケル・オンダーチェ『名もなき人たちのテーブル』、ラナ・シトロン『ハニー・トラップ探偵社』、リチャード・フライシャー『マックス・フライシャー アニメーションの天才的変革者』、ジョン・バクスター『ウディ・アレン バイオグラフィー』(以上作品社)他多数。 — 本書より引用